Nature Remoって、便利そうだけど…
種類ありすぎて結局どれ買えばいいの?ってなっている方は、私だけじゃないですよね?
スマートホーム化の第一歩として「とりあえずRemo入れとけ」ってよく言われるけど、
いざ調べ始めると意外にもモデルが多い・・!
「Remo 3?mini?Lapisって何者?」みたいな状態に。
私も最初は混乱しました。
正直言ってスペック表は数字だらけだし、Amazonのレビューもよくわからん・・。汗
ということでこの記事では、Nature Remoシリーズを「何が違うの?」「自分に合うのはどれ?」
という視点で比較しつつ、あなたが後悔せず選べるような情報を整理してみました。
モデル比較
Nature Remoには現在、主に5つのモデルがあります。
価格も機能も見た目もバラバラで、「どれが正解なの?」と迷ってしまいますよね。
ということで、まずは主要モデルを横並びで比較してみましょう。
表のあとにはどのポイントを重視すべきか?を解説していきますので、まずはざっと全体感をご覧ください。
Nature Remoシリーズ 比較表(2025年5月時点)
Nature Remoシリーズの各モデルの違いを明確に整理し、それぞれの機能や特徴を比較した一覧表を作成しました。これにより、どのモデルが自身の利用シーンに最適かを判断しやすくなります。
| モデル名 | 推奨ユーザー | 価格 | センサー数 | Matter対応 | 環境性能 |
|---|---|---|---|---|---|
| Remo nano | 操作だけしたい | 4,980円 | 0 | 最大3台接続可 | ― |
| Remo mini2 | 初心者向け | 6,480円 | 1(温度) | ― | 基本的な温度制御のみ |
| mini2 Premium | 広い部屋向け | 6,980円 | 1(温度) | ― | 基本的な温度制御のみ |
| Remo Lapis | 節電重視 | 7,980円 | 2(温・湿) | 最大20台接続可 | ◎ オートエコ+コスパ起動あり |
| Remo 3 | 自動化ガチ勢 | 9,980円 | 4種全部 | ― | センサーは多いが最適化なし |
表の中では、価格・搭載センサー・対応アシスタント・スマートホーム連携の違いなど、選ぶうえで重要なポイントをピックアップしています。
機種によっては「Matter対応」や「照度・人感センサー付き」といった上位機能がある反面、「とりあえず使ってみたい」だけなら廉価モデルでも十分です。
モデル選定のポイント|あなたに最適なRemoを選ぶために
Nature Remoシリーズは「どれを選んでも似たように見える」かもしれませんが、
実はモデルごとに搭載されている機能や対応範囲が大きく異なります。
選ぶべきポイントは以下の4つ。
それぞれが暮らしにどう影響するのか、順に詳しく解説していきます。
モデル選定時にチェックしたい項目4選
- センサーの有無
→ 温度・湿度・照度・人感のうち、どれを使いたいか?自動化の幅が大きく変わります。 - 赤外線の到達距離
→ 広い部屋や複数の家電を操作したいなら、赤外線の強さも重要な判断軸です。 - スマートホーム連携性(Matter対応含む)
→ Apple Home/Google Home/Alexaなど、自宅の環境に合わせてスムーズに連携できるか? - 環境性能(Lapis独自の省エネ機能)
→ オートエコ/コスパ起動の有無で、快適さと節電の両立ができるかどうかが変わります。

ここから先は、この重要な4つのポイントを掘り下げてご紹介します。
自分の暮らしや家族構成に合った「ちょうどいい1台」を見つけてください!
| 評価軸 | 具体的に見るべき点 | これを選ぶとどう生活が変わる?(ベネフィット) |
|---|---|---|
| センサーの有無 | 温度・湿度・照度・人感のどれが必要か? | エアコン・照明・加湿器などが“勝手に動く”暮らしが実現。手がふさがる場面でも快適。 |
| 赤外線到達距離 | 家電まで赤外線がしっかり届くか?遮蔽物に弱くないか? | 離れた場所から複数家電を1台でまとめて操作。設置場所の自由度が上がる。 |
| スマートホーム連携性(Matter含む) | Apple Home/Google Home/Alexaでどれだけ操作・連携できるか? | 複数メーカーのスマート機器がまとめて動く。音声・アプリ・自動化を横断的に使える。 |
| 環境最適化機能(Lapisのみ) | オートエコ/コスパ起動のような省エネ制御があるか? | 快適さを保ちつつムダをカット。エアコンの「つけっぱなし」「効きすぎ」がなくなる。 |
センサーの有無「操作自動化対象拡張力を強化」
見るべき点:温度/湿度/照度/人感のうち、何を使いたいか?
Nature Remoシリーズはモデルによって、搭載されているセンサーの種類が異なります。
センサーは、自動化を実現するための「トリガー(きっかけ)」となる重要な要素です。
主なセンサーの種類と役割
| センサー | 検知する内容(役割) | 実際の使い方(機能例) |
|---|---|---|
| 温度センサー | 室内の気温の変化 | 室温が28℃を超えたら冷房ON |
| 湿度センサー | 空気中の湿度レベル | 湿度が40%を下回ったら加湿器ON |
| 照度センサー | 明るさ(光の強さ) | 暗くなったら照明ON |
| 人感センサー | 人の動き・在不在 | 人がいなくなったらテレビOFF など |
気になる使い方例はありますか?モデルの選定をするときに何を重視するのか、を選ぶつもりでこの先もご覧くださいね。
暮らしの変化例
「リモコンを使う生活」から、「家電が勝手に動く生活」への変貌。
センサーを搭載したモデルを選ぶことで、操作の手間が限りなくゼロに近づきます。
暑くなったら勝手にエアコンが起動する、と言うのは基本として
「夕方暗くなってきたら照明オン、ついでにカーテンも閉まる」(照度センサー)
「書斎の椅子に座ったら仕事集中モードが起動、デスクライトが起動して音楽も起動する」(人感センサー)
といった形でさまざまな自動化のトリガーとして使うことができます。
特に子育て中や就寝時など、手が離せないタイミングでの“自動で快適”は強い味方になりますよ。
他社スマートデバイスとの連携も可能に!
センサーを搭載したRemoモデルであれば、Google HomeやAlexaなどのプラットフォームを通じて、
スマートロックやカーテン、他社製照明などとの自動連携も可能になります。
直接センサーを介した操作はしなくとも、「Remoのセンサー」を起点にして家全体の自動化を広げていく拡張性を強化することができるのが大きな魅力のひとつです。
赤外線強度|1台で家中の家電が動くか?
見るべき点:部屋の広さや家電の数に対して赤外線がしっかり届くか?
Nature Remoは赤外線リモコン家電を操作するためのデバイスですが、
モデルごとに赤外線の出力や到達距離が異なります。
これは、「1台で何台の家電をカバーできるか?」「どこに設置すべきか?」に大きく影響します。
私自身赤外線なんて遮蔽物がなければ届くだろう、と思っていたのですが
リビングの端に本体を設置した結果対角線上の照明を操作できないという事態に陥りました。
子育て世帯では一般的に部屋が広くなりがちの傾向にありますので見落とさないように注意してくださいね。

当時はなぜ操作ができないのか原因がわからず非常に苦戦しました・・。
モデルによって対応距離が違うことも覚えておきましょう!
赤外線出力と設置の目安
| 性能グレード | 到達距離の目安 | 適した環境 |
|---|---|---|
| ミニマム(nano) | 赤外線出力が控えめ/近距離向け | 一人暮らしのワンルームや小さめの部屋向け |
| 標準(mini2/Lapis/Remo3) | 一般的な家庭向け出力(明確な距離は未公表だが5m〜10m程度) | 6〜8畳程度の部屋で、TV・照明・エアコン操作に |
| 強力(mini2 Premium) | 出力強化/広い部屋や遮蔽物に強い(10〜20m超) | リビング・複数家電操作に対応しやすい |
ちなみにこちら、到達距離の具体的な記述が公式ページにはないのですよね。
赤外線強度30畳程度・・ってなんやねん!と突っ込みました。
と言うことで参考になるかは分かりませんが、我が家の事例を紹介しておきます。
こちらの写真はうちのリビングRemoの設置場所から照明に向かって撮影したものです。

距離を測ってみたところ5.5mほど離れておりました。
今の家に引っ越しをしたときに以前から使っていたnanoモデルをここに設置をしたのですが、
手前の照明は操作ができるのに奥の照明がまるで反応せず。
(遮蔽物はなし、本体から正面に向けて設置をしています。)
その後照射距離に違いがあると言うことに気づき、mini2へ変更をしたところ綺麗に操作ができるようになりました。この点から、nanoモデルは5m程度距離が空くと操作不可、mini2は5m以上でも問題なく操作が可能、と言うことは間違い無く言えると思っています。
暮らしの変化例
家電ごとにリモコンを使い分けるストレスから解放。
赤外線照射性能が高いモデルなら、1台でテレビ・エアコン・照明などの操作がまとめてできるため、
「リビングに1つ置くだけで全部操作できる」という体験が可能になります。
また、強出力モデルは赤外線が反射しやすいため、壁や家具越しにも届くことが多く、設置の自由度も高いです。
🔍 設置トラブルを防ぐポイント
- 小型モデル(nanoなど)は「届かない」「反応しない」という声も少なくない
- 「テレビは反応するのにエアコンは反応しない」などの差もあり
- 高出力モデル(mini2 Premium)はその点で安心感が高い
1人暮らしや「リモコン機器を1つだけ操作したい程度」なら標準出力モデルでもOKですが、
複数の家電を自動化したい/家族全員で使いたい場合は、赤外線の強さも重要な選定ポイントになります。
スマートホーム連携性|未来への拡張性
見るべき点:「声・アプリ・他デバイス」どこまで連携できるか?
Nature Remo単体でも赤外線家電の操作はできますが、
スマートスピーカーや他社のスマートデバイスと連携できるかどうかはモデルによって異なります。
その違いが、将来のスマートホーム広がり(拡張性)に直結します。
前述のセンサー種類や性能にも大きく関わってくるので将来的に何ができるのか?と言うのはイメージを膨らませておくと良いかもしれません。
スマートホーム連携性の3つの側面
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| Matter対応 | SiriやApple Homeと連携できるか(nanoのみ対応) |
| 音声アシスタント | Alexa/Google/Siriのうち、どれと連携できるか |
| 自動化シナリオ | 他社デバイス(SwitchBot、Aqara等)と組み合わせられるか |
例えばこんなことを考えてみると良いでしょう👇
「OK Google、ただいま」で照明+エアコンON
iPhoneショートカットで「帰宅ボタン」を押すとブラインドが閉じて、加湿器が起動
人感センサーで家電+ロックが同時に動く
Q. Matter対応って何?何が変わるの?
A.スマートホームの“共通言語
Matter(マター)とは、Google・Apple・Amazonなどの大手が協力してつくった、
「どのメーカーのスマートデバイスでも一緒に使えるようにするための共通規格」です。
スマート家電メーカーが乱立した結果
確かに便利なんだけど・・・
「この照明はGoogleアプリでしか動かない」「エアコンはメーカー専用アプリからじゃないと操作できない」など、
メーカーやアプリがバラバラで統一できないのが悩みでした。

この悩みを解決してくれるのがMattarです!
対応製品を揃えれば簡単に一つのアプリでまとめて操作ができるようになりました!!
もちろんMatter非対応モデルでもGoogle Home/Alexa経由で一括操作は可能ですが、
初期設定に工夫が必要だったり、アプリをまたぐ設定になることも。
Remo nanoのようなMatter対応モデルであれば、
Apple Home・Google Home・Alexaなどの主要スマートホームアプリから、
直接操作・一括連携・音声コントロールがすぐに使えます。
暮らしの変化例
家電単体の操作から、“暮らしごと動かす”体験へ。可能性は無限大に拡がっていく。
Matter対応モデル(nano)を選べば、iPhoneやSiriから直接操作が可能になり、
Apple製品中心の家庭では特に快適さがアップします。
また、センサー付きのモデルとGoogle Home/Alexaを組み合わせることで、
赤外線製品だけでなくカーテン・鍵などを一括で動かすシナリオを構築できるようになります。
何よりも大きいのが、通常のRemoの操作はクラウドサーバーからの指令を介して赤外線を発信します。
一方、Matter対応モデルだと自宅のLAN内で操作を完結することが可能になります。
少々伝わりにくいかもしれませんが、通常モデルの場合
Remoクラウドサーバーに不具合が発生していると操作ができなくなってしまいます。
Matter対応製品だとRemoのサーバーがダウンしていても自宅のアプリから直接操作が可能になるイメージです。
専用アプリを使わずに、家中のデバイスを自然にまとめられる使いやすさと障害発生時に対するレジリエンスが大きな魅力です。
誤解しがちなポイント
- Remo自体が「スマートロックを操作する」わけではありません
- センサー付きモデルを“トリガー”として使う → プラットフォームが連携機器に命令するという流れです
- よって「連携性」は、センサー+対応プラットフォーム+Matterの有無の“総合力”で決まります
今は「とりあえずエアコン操作だけ」であっても、いずれ照明や鍵、カーテンもスマート化したくなったときに備えて、連携性の高さは“未来の選択肢”を残せる安心材料になります。
あまり深く考えすぎるとどんどん難しくなるのであくまで将来に向けた投資を必要とするか?と言う観点で見ていただければと思います。
環境性能・省エネ機能|快適さと節電を両立するモデルか?
見るべき点:温度調整が「できる」だけで満足?それとも「最適」に使いたい?
Nature Remoの各モデルには、温度センサーやタイマー機能を活用して
時間帯による運転/一定温度でのON/OFF制御/消し忘れ防止といった、
“基礎的な節電自動化”はどのモデルでも実現できます。
センサーを組み合わせるとさらに細かい設定が可能ですね。
しかし、Remo Lapisはその一歩先
「快適さと省エネを両立させるための最適化」ができる唯一のモデルです。

公式ページでも環境性能を謳っているだけあって力の入り方が段違いです!
Lapisだけの高度な省エネ制御
公式でも力強く環境性能を謳っている同機種ですが、
大きく分けると目玉は二つ「オートエコ機能」と「コスパ起動」です。
| 機能名 | 内容 |
|---|---|
| オートエコ機能 | AIを活用したより賢い自動節電システム。ユーザーが節電強度を選択すると機器が自動で節電を行ってくれる。 |
| コスパ起動 | エアコン起動時、急速に設定温度に持っていくのではなく、30分程度かけてゆっくり温度調整を行うことで省パワー化が可能。 |
| 消し忘れアラート | 自宅に誰もいない状態が長時間続くとあなたのスマホに通知を出してくれる機能。消し忘れ通知を出すまでの時間を設定することも可能。 |
他モデルにも「温度でエアコンON/OFF」「スケジュール実行」は可能ですが、
Lapisなら“効かせすぎ”や“長時間つけっぱなし”を抑えつつ、快適さはそのまま。
我慢せず自然に節電を実現できるのが大きな違いです。
暮らしの変化例
体感温度はそのままに、ムダだけを自動で減らしてくれる。
- エアコンの風を直接当てずに“空間の空気を保つ”制御
- 湿度の変化まで加味して、乾燥しすぎやジメジメ感も防止
- ピーク時間帯を外した起動で、電気代の最適化
Remoシリーズ全体でも「スマートに家電を動かす」は当たり前になっています。
Lapisはそこから一歩進んで、“賢く・やさしく”動かす家電制御を目指したモデルです。
快適さ・電気代・環境負荷――全部気になる人には、Lapisが答えになります。
モデル選定のヒント
あなたに合うRemoモデルはこれ!かんたん診断チェックリスト
ここまではモデルの特徴と評価軸を見てきました。
そうはいってもどうやって選んでいいのかわからない?というあなたにサポートチェックリストを用意しました。
以下の質問に「YES」が多かった項目をもとに、あなたに合うモデルを見つけてみましょう。
【質問 1】スマホ1つで、すべての家電をまとめて操作したい?
- YES → Matter対応モデルがベスト。Apple Homeやショートカットと相性抜群。
- NO → Google HomeやAlexaを使っている場合はmini2/PremiumでもOK
【質問 2】部屋の暑さ・寒さにあわせて、エアコンが自動で動いてほしい?
- YES → 温度センサー搭載モデル(mini2以降)を検討しよう。
- さらに「省エネや湿度も気になる」なら → Lapisがおすすめ。
【質問 3】テレビ・エアコン・照明…すべて1台でカバーしたい?
- YES → 赤外線が強いモデル(mini2 Premium)を選ぼう。
- NO → 対象の家電が1〜2台ならnanoでも十分対応可能
【質問 4】将来、スマートロックやカーテンも導入する予定がある?
- YES → 連携のしやすさを考えて、Matter対応(nano)やセンサー付きモデル(Remo 3)が有利
- NO → 今使っている家電に合わせて必要最小限のモデルでOK!
【質問 5】家族や実家の親にもお勧めしたい?
- YES → 音声操作ができるスマートスピーカーの導入(全モデル対応/nanoはSiri可)がおすすめ。
- 「Apple製品中心」なら→Remo nano もしくは Remo3 を推奨。
✅ このチャートで伝えたいこと
- 自分の生活スタイルや部屋の構造にあわせて、「どの機能が必要か?」を選ぶのが正解
- ステップアップも無駄にならない設計(例えばnanoをサブ機として残すなども◎)
- 高機能=正解ではなく、“ちょうど良さ”が見つかるラインナップ構成になっている
👉こんな“ステップアップの選び方”もあり
私がガジェットを選ぶときは最廉価機種の機能をスタートにして費用を追加するとどんな機能が手に入るか?というのを確認するようにしています。

最終的には必須の機能とお財布と相談をしてちょうどいいところを探します。
スペック表を見ながらウンウン唸るのが至福のひととき!!!
今回のケースでいえば以下の流れで全体を精査して何が欲しいかを考えます
- 「いくらプラスしたら、どんな機能が手に入るの?」を整理してひと目でわかるようにする。
- 「今の暮らし」に合った1台をまず導入してみる
- しばらく使って機能が足りないと感じたら別部屋に移してサブ機化し、より上位モデルを追加という形もアリ!
ゆこたんオススメ機種はRemo mini 2
ここまで長々と記事紹介を書いてきましたが、私が選んだのは、Remo mini 2です。
正直機能的にはそれほど充実はしていませんが、実際に使ってみて“ちょうどよかった”と感じています。
考え方は以下の流れ。
- まずはnanoで「スマホから家電を操作する」を快適さを想像する
- mini2(+1,500円)にすると?→温度トリガーを導入。暑くなるとエアコン起動が可能!
- mini2 Premium(+500円)は?→赤外線強化。広い部屋を全て網羅!
- Lapis(+1,000円)→ 環境性能追加。エアコン制御の最適化が可能、電気代削減!
- Remo3(+1,000円)→すべてのセンサーが追加。暗くなったら照明点灯、など夢が広がる!
今回紹介している評価軸の中で私が重視している点を紹介していきましょう。
評価軸①:赤外線強度
先ほども紹介をしましたが、最初はnanoを購入して使用していました。
現在の家に引っ越しをした後テレビは反応するけど、奥の照明が反応しないという状況が発生。
mini2モデルに更新すれば赤外線が強力になるということで、部屋の端でもしっかり反応してくれる安心感を評価しました。
評価軸②:温度センサー付き
私はガジェットオタクを自負しているので、いろいろな拡張性を持たせたくなってしまう性質があります。
照度センサー、人感センサーもとても惹かれたのは事実です。
最初はRemo3で遊びまくってヒャッホーーーイ!としたかったのですが。3,500円・・・💦
正直なところ、
照度センサー:暗くなったら照明ON→点灯時間を設定すれば代用可能。
(そもそも家に誰もいないのに照明点灯しても意味なくない?)
人感センサー:ちょっと部屋を開けただけでエアコン止められても困る・・
(今回はリビングで使う想定なのでそれほど需要が感じられませんでした。)
ということで、最終的にどうしても外せない機能
「部屋の温度をあげすぎないように30℃を超えたら冷房を入れたい」
キッチンの常温保管の食材が悪くならないようにしたい、が目的です。
個人的にはこれができるだけで生活の質は爆発的に向上すると思っています。
評価軸③:Matter対応
正直に言います、Matter。つい最近まで知りませんでした。
現在Google Home中心で運用していますが、当初特に問題なく一括操作ができていました。
問題が発生したのは一昨年の真夏・・Remoサーバーに障害が発生。
この時に知ったのですが、
無線LAN端末、インターネット回線、Remoサーバーどれか一つでも障害が発生すると
全く操作ができなくなってしまうリスクがある、ということ。
Matter対応製品を使うとクラウドサーバーではなく、家のスマートホームから直接指令を出すことができるため、
仮にクラウドサーバーがダウンしても問題なく操作を継続することができます。

真夏にエアコンの電源が入れられないのは生命に関わります・・!
ということで、寝室にはMatter対応のnanoを配置しています
実際使ってどうか?
正直、最初は懐疑的だったのですが、毎日「操作しなくていい快適さ」を実感しています。
「リモコン、どこ?」がなくなっただけでもありがたいです。
何より、自分の生活にあわせて少しずつ自動化が増やせる感覚は、ちょっとした未来感もあります。
私は自分の人生がどんどん変わっていく、今までできなかったことができるようになる、
という実感が前向きな改善の活力につながっていく、と思っています。
ちょっとした買い物で人生が別のものになっていく、という感覚をあなたにも感じて欲しいです!
迷う前に買ってみよう
Nature Remoの各モデルには、それぞれに“ちょうどいい強み”があります。
だからこそ、「ベストな1台」は人によって違います。
・・でも、1つだけ確かなことがあります。
Remoは“買ってから気づく快適さ”がある。
ーー ⛏️スマートホームって、最初の1歩がいちばんむずかしい ーー
「設定とか、連携とか、難しそう。」
そう思うのもわかります。
でもちょっと待ってください・・!
Remoなら、スマホとリモコンがあれば、すぐに“最初の自動化”が始められます。
まずは1台。リビングに置いてみるだけで、生活はちゃんと変わります。
実際に使い始めてみて、
「あ、これもっと早く導入しておけばよかった…」と思った人は少なくありません。
我が家でも最初は懐疑的だった妻もいつの間にか使い始めて、私よりも使いこなしています(笑)。
それくらい、「操作の手間をなくす」「快適さを自動で維持する」って、暮らしに大きな変化をもたらしてくれるんですよね。
あなたにもぜひ一度新しい生活に身を投じてみて欲しいです。
まとめ|Remo選びのポイントをもう一度
- モデルによってできることが違う(センサー・赤外線・連携性・省エネ機能)
- ステップアップしやすい価格構成
- 生活スタイルや家族構成にあわせた選び方ができる
そして何より…
「めんどくさい」を「勝手にやってくれる」に変えることが、
自分の時間と心の余裕を取り戻す第一歩になります。
本記事があなたの時間を取り戻す一助になれれば嬉しいです。
Remoの各モデルはこちらからチェックできます
- Nature Remo nano(Matter対応)公式ページ
- Nature Remo mini2 公式ページ
- Nature Remo mini2 premium 公式ページ
- Nature Remo Lapis(オートエコ対応)公式ページ
- Nature Remo 3(全センサー搭載)公式ページ

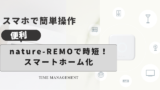


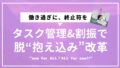
コメント